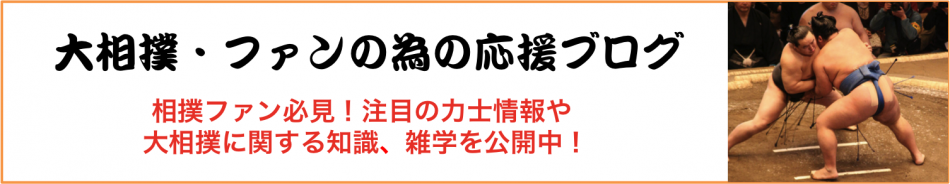大相撲の懸賞金は1本いくら?最高額や税金について!

大相撲の懸賞金について気になった経験はありませんか?
取組後にもらえるあの袋の中には、
一体どれだけの額のお金が入っているのでしょう・・・
この記事では、
そんな大相撲の懸賞金が一本いくらなのか、
またその最高額や最高本数をはじめ、
税金がとられるのかについてもご紹介します。
大相撲の懸賞金は1本いくらなのか?税金もかかるの?
相撲の懸賞金は、1本62,000円になります。
この中から、協会への手数料として5,300円が差し引かれるため、
力士がもらえるのは56700円になります。
協会の手数料の内訳としては、
取組表への掲載料や場内放送料、
および企業や団体名などのキャッチコピー費となります。
その中から、力士が直接もらえるのは30000円となります。
では、差し引き26700円はどういう内容のお金でしょうか。
この26,700円は勝ち力士本人名義の預かり金として
日本相撲協会が積み立てるために預かるようです。
それは、本人の税金に回るそうで、
余ったら引退後にもらえるようです。
これは私の感想ですが、取り組み後の勝者・勝ち力士が、
のし袋が幾重にも重なった束を受け取るのを見ると、
つい、あの中に生の現金が入っていると考えてしまいます。
一般社会では考えられない事ですし、
見ていてよだれが出るくらいです。
汚い話しで恐縮ですが、本当に、豪快な世界、
浮世離れした相撲の世界のようです。
羨ましい限りですね。
名勝負になると、勝ち力士自身が、
両手で受け取らないと持てないくらいのこともありました。
では、これまでの懸賞金の最高本数と最高額は
一体どれ位のものだったのでしょうか。
以下で詳しくご紹介していきます。
大相撲の懸賞金の最高本数と最高額はどれ位なのか
これまでの懸賞金の最高本数と最高額は、
以下5つの取組における
本数は61本、金額にして183万円という額になります。
・15年1月の白鵬-鶴竜戦
・同年9月の鶴竜-照ノ富士戦
・16年5月の稀勢の里-鶴竜戦
・17年1月の白鵬-稀勢の里戦
・同年5月の稀勢の里-御嶽海戦
力士1人につき3万円を受け取れる事になるので、
これらの取組に勝利した力士はたった1日で、
なんと93万円という額を受け取ったという事になります・・・。
相撲の世界は、私たち一般人の住む社会とは、
金の見せ方使い方が、随分違うと感じますね。
この懸賞金ですが、本来であれば
取り組み1つにつき50本という制限があります。
言われてみるとわかりますが、
土俵上を懸賞旗が、何分も回っていたら、
観客も力士も、集中力が欠けてきて、
相撲の中身もなんだかなあってことになりかねません。
そうなると、相撲人気の凋落にも繋がりかねません。
制限をつけるのは当たり前ですね。
ただ平成27年1月の白鵬の場合、
6場所連続優勝という記録がかかっていた事情があり、
特例として制限を解いたという事情があります。
一方の鶴竜も初優勝がかかっていたという事情がありました。
なお、これらの取組み以外で懸賞本数が多かったのは、
20年1月場所の貴景勝-徳勝龍戦の60本になります。
この取組で徳勝龍は勝利し、
幕尻優勝を果たしています。
ちなみに「1場所」での懸賞金の最高本数は
15年1月場所の白鵬の545本となります。
2〜4位も全て白鵬で、5位の鶴竜は438本(15年9月場所)となっています。
個人の年間記録も10年の白鵬2111本が首位。
こちらにいたっては2〜5位も全て白鵬が独占しています。
これは力士の強さと懸賞金の本数が比例していると言えますし、
当時の白鵬が、どれだけ別格の強さを誇っていたかを示す
エピソードになるとも言えますね。
この記事のまとめ
相撲の世界は、私たち一般人の住む社会とは、
金の見せ方使い方が、随分違うと感じますね。
大きな肉布団を身にまとった男たちが、
土俵上で、力一杯ぶつかり合う、
そんな真剣勝負が繰り広げられる
一種独特な格闘技の世界です。
懸賞金は、あくまでも懸賞金であり、
給料とは別物扱いです。
ある意味目の前にぶら下げられたにんじんであり、
勝利へのモチベーションに繋がるものでもあります。
私たちの一般社会でも、お祭り気分で、
金額の多寡ではなくこんな懸賞金があれば、
もっと、楽しく仕事が出来るような気がしますね。